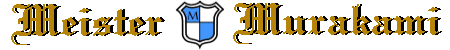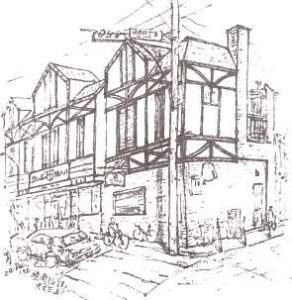ハム・ソーセージ豆知識
1. 日独英のハム・ソーセージ
| 日本語 | ドイツ語 | 英語 |
|---|---|---|
| ハム | Schnken (シンケン) | Ham (ハム) |
| ソーセージ | Wurst (ヴルスト) | Sausage (ソーセージ) |

2. ハムのおはなし
本来、ハムとは「豚のもも肉を塩漬け燻煙したもの」をいいます。
したがって、ボンレスハムや骨付きハムがハムに該当します。
日本では、「豚の背肉(ロース)を塩漬け燻煙したもの」をロースハム といっています。
ロースハムは、日本独特のハムで日本農林規格(JAS)で定められています。
3. ベーコンのおはなし
本来、ベーコンとは「豚のばら肉」の意味ですが、一般には、「豚のばら肉を塩漬け燻煙したもの」をベーコンといいます。
4. ソーセージのおはなし
ソーセージの語源には、Sau(牝豚)とSage(香辛料のセージ)という語が合成されてできたという説や ラテン語のSalsus(塩漬け)からきたという説など諸説があります。
日本農林規格(JAS)によるソーセージの定義は多岐にわたりますが、 簡単に表現するならば「豚や牛などの肉に香辛料などを混ぜケーシング(包装材)につめたもの」 といえます。
日本では、一般に腸詰(腸をケーシングにして詰めたもの)をソーセージと呼んでいます。
ソーセージの名前
ソーセージにはヨーロッパの地名を商品名に付けたものが多く見られます。 ソーセージは、それぞれの地方により確固たる製法があり、それを表すのがソーセージの名前なのです。
| 製品名 | 説明 |
|---|---|
| ボロニアソーセージ | イタリア中部のボロニア地方の代表的なソ-セージ |
| フランクフルトソーセージ | ドイツのフランクフルト地方の代表的なソ-セージ |
| ウィンナーソーセージ | オーストリアのウィーン地方の代表的なソ-セージ |
| リオナーソーセージ | オーストリアのウィーン地方の代表的なソ-セージ |
しかし、日本農林規格(JAS)では下記の表のように「分類の名称」として使われています。
| 分類名 | 概要 |
|---|---|
| ボロニアソーセージ | 牛腸を使用したもの。又は製品の太さが36mm以上のもの |
| フランクフルトソーセージ | 豚腸を使用したもの。又は製品の太さが20mm以上36mm未満のもの |
| ウィンナーソーセージ | 羊腸を使用したもの。又は製品の太さが20mm未満のもの |
| リオナーソーセージ | ソーセージに野菜、穀物、肉製品、チーズなどを加えたもの |
| レバーソーセージ | 肝臓を使用したソーセージ(重量の割合で50%未満) |
| レバーペースト | 肝臓を使用したソーセージ(重量の割合で50%以上) |
ソーセージの製造方法
本場ドイツでは、ソーセージを製造方法により4つに分類しています。
| 分類名 | 直訳 | 概要 | 製品例 |
|---|---|---|---|
| ブリューヴルスト | 茹ソーセージ | 細切りした生肉に、飲用水(氷)、塩、脂肪を添加し加熱処理したソーセージ | ウィンナー、フランクフルト、ボロニアなど |
| コッホヴルスト | 煮ソーセージ | 細切りした生肉に、飲用水(氷)、塩、脂肪を添加し煮沸処理したソーセージ | レーバーソーセージ、ブラッドソーセージなど |
| ローヴルスト | 生ソーセージ | 消費されるまで生で貯蔵されるソーセージ | サラミなど |
| ブラートヴルスト | 焼ソーセージ | 加熱してから食べる保存性の短いソーセージ |
日本では、これに1対1で対応する分類はなく、日本農林規格(JAS)の製造法による分類は次のようになっています。
| 分類名 | 概要 |
|---|---|
| クックドソーセージ | 湯煮又は蒸煮により加熱したソーセージ |
| ドライソーセージ | 加熱しないで乾燥したソーセージ(水分が35%以下) |
| セミドライソーセージ | 加熱又は加熱しないで乾燥したソーセージ(水分が55%以下) |
| 無塩漬ソーセージ | 塩漬していないソーセージ |
参考文献
食肉用語辞典(日本食肉研究会編)
フライシャー・マイスターの専門知識(食肉通信社)